海外の方に日本のイメージを聞くと、必ず「ロボット」という言葉が出てきます。もちろんロボットといってもさまざまですが、食事を運んでくれたり、話し相手になってくれたりと、それぞれの用途に合わせて開発・製作されています。
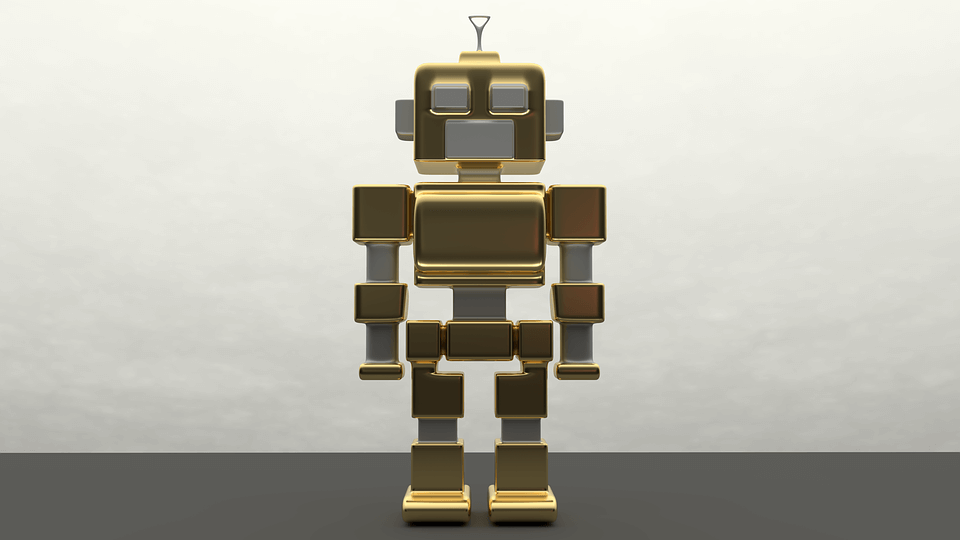
ビジネス的な視点で見てロボットの活躍は著しく、中でも「協働ロボット」は生産工程を大幅に軽減してくれる頼もしい味方でもあります。ここでは生産工場や作業場での人気者「協働ロボット」に密着し、注目度が高まっている背景とその驚愕の働きぶりをご紹介します。
そもそも協働ロボットとはどんなもの?
一般の生活ではあまりお目にかかれない「協働ロボット」。一体、どのようなものなのでしょうか?
人と一緒に働くロボットのこと
協働ロボットは一言で表すと「人と一緒に作業するロボット」のことです。作業員の横に並んで一緒に作業を担当してくれるロボット、つまり「スタッフと協力して働いてくれる」のが最大の魅力となります。
もちろん、導入する際にはリスクに対する的確なアセスメントを用いることが必要不可欠となりますが、法律の上でも安全柵を使用する必要がありません。以前からの課題であった作業員のスペースを確保して、ロボットを隔離する必要がなくなったということになります。
その背景として、2013年に産業ロボットに対する規制が緩和したことが挙げられます。この時点ですでに80ワットを超える産業ロボットでも、開発メーカーや使用者がISOの定めるハンドガイドや動力などの制限に遵守していれば、囲いを用いなくても使用できるようになりました。
「コボット」の愛称で知られる
協働ロボットは英語の「collaborative robot(コラボレイティブ・ロボット」の略称で「cobot(コボット)」とも呼ばれています。通常では不可能だった「小ロット生産」や「多品種生産」を可能にし、コスト削減に大きく貢献してくれる頼もしい産業ロボットの一種です。
コボットの性能は日々高まっています。実際、コボットの開発・製作においては、作業員がコボットに触れたり、作業台や周囲の何かに触れてしまった時に停止する「安全機能」を備えています。この点においては、前述しましたISO規格にある「安全適合監視停止」の項目を確実にカバーしていることになりますね。
協働ロボットを向上に導入するメリットは?
企業が投資をしてでも手に入れたい協働ロボット。さて、導入に対するメリットは一体何なのでしょうか?
プログラミングの難易度が以前より大幅に改善
作業場で人と並んで仕事をしてくれるコボット。企業が検討する理由に「プログラミングが簡単である」ということが挙げられます。従来の産業ロボットに作業工程をプログラミングするには時間がかかっていました。また、プログラミングをするには、ある一定の知識を持つ特定の人しかできないという問題もありました。
もちろん、協働ロボットにも色々あり、まだまだプログラミングが難しいタイプのものもありますが、現代では一般のオペレーターでも比較的簡単にセットアップができるようになっています。設定シーンにおいても動作的な部分を確認しながら、タッチスクリーンを用いてプログラミングを進めていくことができます。おおむね、協働ロボットへのプログラミングも一日足らずで完了できます。中には半日で終了するタイプもあるほどです。
省スペース・軽量である
協働ロボットといっても、アニメや漫画で登場するような巨大ロボットではありません。中にはアーム型や人よりも小さなものもあります。つまり、大きなスペースを用意なくても、作業員数名(モデルによっては一人分程度)のスペースがあれば、十分に設置できるということです。例えば、大規模な生産工場ではさほど心配はありませんが、町工場や限られたスペースしか確保できない環境では、スペースの問題はかなり深刻です。そうなると、協働ロボットのように省スペースで使用できるロボットは重宝するでしょう。
また、協働ロボットは「軽量」です。フォークリフトがなくても別の場所へ移動することができます。軽量ということはメンテナンスも容易で保管にも手がかからないと言えますね。現代の生産工場で欠かせない「フレキシビリティ」にも貢献しています。
産業ロボットとの違いは?
ここで改めて、協働ロボットと従来の産業ロボットを比較してみたいと思います。さて双方にはどのような違いがあるのでしょうか?
危険エリアがあるか、ないか
協働ロボットと似たような仕事をしてくれる「産業用ロボット」は、車体工場や商品の生産工場などで現在でも導入されています。サイズが格段に大きいというわけではないのですが、近くで作業をするスタッフや作業場での安全を確保するために、囲いを用いなければならないといった厳しい規則があります。わかりやすく言うと、産業ロボットには「危険エリア」と呼ばれる領域があり、周囲を柵で覆い一般の人が入れないようになっています。
シンプルな作業内容にのみ対応、柔軟に対応
協働ロボットに比べると、産業ロボットはシンプルな作業が多いです。作業員が産業ロボットと連携して一つの行程を終わらせるということは少なく、むしろ産業ロボットが単体で一つの仕事を完結させるようなシチュエーションで用いられます。産業ロボットは人と一緒に作業をするような行程で採用するわけではなく、至って単純な作業を任せる場合に活躍します。また、産業ロボットは柔軟な作業が苦手であるため、複雑な動作に対応できないこともあります。
大型ラインで導入、小規模ラインでもOK
協働ロボットは作業スタッフと一緒に並んで仕事をしてくれるため、設置場所を選ばないという特徴があります。つまり、大型ラインでも作業台でも、どこでも与えられたタスクを処理してくれる上、異なる種類や量にも対応してくれます。一方、産業ロボットの場合は大型ラインに導入されることが多いため、同じ品種で大量生産を行う時に好んで導入されます。
協働ロボットの作業クオリティはどうなの?
協働ロボットの魅力や特徴、そして導入へのメリットについてお話しましたが「ロボット作業による品質はどうなの?」と、タスクの精密さや最終的な品質などについて不安を感じることもあるでしょう。
そもそも協働ロボットは、人と一緒に二人三脚で仕事をこなしてくれるロボットを意味します。つまり、プログラミングされたタスクを人の横に並んで流れ作業で行っていくのが仕事です。そのため、最終的なクオリティに関しては「人間の目」で行うのが基本となります。そうとは言いながら、今まで2名の作業員で行っていた仕事を1名の作業員と1台の協働ロボットで行えば、人員不足の解消や仕事の効率化、さらにはコスト削減につながることは間違いありません。
協働ロボットは、言ってみれば「アシストロボット」といった位置づけにあるとも言えるでしょう。作業ラインを止めることなく、一定のスピードで滑らかに順調に行っていくことができ、何より「力仕事」を任せることができます。この「力」の必要な部分を協働ロボットにお願いして、逆に、軽作業にあたる箇所を別の作業員に行ってもらう、または力の限られている女性スタッフに任せるといったことも可能です。
まとめ
「コボット」の愛称で親しまれている協働ロボットは、工場内のヒーローになりつつあります。生産工場が直面している課題をスッキリ解消してくる強い味方です。最終確認は人の目で行い、品質管理に徹底しながら、コボットを有効的に活用していきましょう






